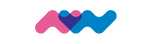音が気にならない方法ってある?
と気になっている方
この記事では
- 音の豆知識
- 音が気にならない方法
についてお話していきます。
そもそも音とは何でしょうか?
その性質を知らないのに、音が気にならない方法を見つけるのは難しそうです。
音が私たちにどう伝わっているのか、音が気にならない方法までまとめてご紹介します。
音の豆知識

音は耳で聞いている。
きっと皆さん、そう思われているのではないでしょうか。
私もそう思っていました。
でも実際に音を聞いているのは、耳ではなく脳なんです。
■音は脳が聞いている
- 音が耳の穴(外耳道)を通って鼓膜を震わす。
- 鼓膜が振動して耳小骨に伝えられ増幅されて内耳へ伝わる。
- 内耳に伝わってきた音の振動がリンパ液を揺らし電気信号へ変換する。
- 電気信号が蝸牛神経を介して脳へと伝える。
- その電気信号が音として認識される。
言葉にすると少し難しいですが、これらのことをまとめると、耳は音を伝える器官であり、音を認識するのは脳ということになるんですね。
■音の豆知識
音を計測する時、音の高さ(周波数)・音の大きさ・音色の3軸で考えます。
①音の高さ(周波数)
音の高さとは、1秒間あたり何回音波が振幅するかを意味しています。
数値が高いほど高音になり、数値が低いほど低音になります。単位はHz(ヘルツ)。一般人は、0Hzから20kHzの範囲を聞くことができます。
②音の大きさ
音の大きさは、単位をdB(デシベル)で表します。
一般的に、0dBから120dB程度の範囲で計測されます。これを超えると耳に大きなダメージ(耳の鼓膜が破れる)を与えてしまいます。
③音色
音色は、波形の形そのものから読み取ることができます。
例えば、ピアノとギターで同じ高さの「ラ」の音を同じ大きさで弾いたとします。
これは音の高さも音の大きさも同じです。
しかし、両者の違いは簡単に聴き分けることができますよね。
音の基準となる基音と、基音の周辺で鳴る倍音(上音)の組み合わせで成り立っており、この組み合わせの割合が違いが音色の違いになり、聴き分けることができるのです。
普段は気にしていない音のことをこうして言葉で表しみるとおもしろいですね。
音が気にならない方法

音は耳から伝わり、脳が音を認識している。
そう分かったところで、その音が気にならない方法はあるのでしょうか?
皆さんが工夫している音が気にならない方法をご紹介します。
■耳を自力でON・OFF
仕事してると雑音だらけです。
事務の女性たちはおしゃべりし放題、おじさんは電話の声が大きくてうるさいので、耳をオフにしていないと毎日しんどいです。
慣れてくると自力でON・OFFできるようになりました。
うるさい音を出す人のことをエキストラさんと思うことで、私は克服できました。
■根性論で乗り越える
勉強の時など、音が気になっていても無理矢理続けようとすると、すごく気持ち悪い感覚になるのですが、その気持ち悪い感覚を持ちながらやり続けると楽になる瞬間があります。
それを繰り返すうちに気にならなくなってきます。
■自身の性格と思って諦める
家族と過ごしたり、誰かが寝ている寝息でさえ集中できず、うるさく感じる時があります。
そう感じることを病気というよりは、自身の性格と思って諦めました。
あまりにもストレスがたまったと感じた時は、耳栓を使ってしのいでいます。
EarZzzの耳栓は>>こちら
皆さん色々と工夫して、うるさい音が気にならないようにしていますね。
その他に、音は音でかき消すという方法もあります。
自然の音を聞き、意識をそちらへ向けることで、気になる音をかき消してしまうのです。
例えば、滝・小川のせせらぎ・木の葉の擦れ合う音・波の音など、自然に聞き流せる自然環境音がおすすめです。
EarZzzでは、気持ちがリラックスできたり、前向きになれるような音楽をYouTubeで配信しています。
おやすみ前や休憩時間にぜひお試しください。
【耳の休息ch】耳のしあわせ Music Lab.は>>こちら
まとめ
音の豆知識と音が気にならない方法についてご紹介していきました。
- 音の豆知識は、音は耳から伝わり、脳が音を認識している。
- 音が気にならない方法は、脳を上手くだませたら音が気にならなくなるかもしれない。
耳は音を伝える器官であり、音を認識するのは脳ということを知ったので、音の豆知識が増えましたね。
脳を上手くコントロールすれば、うるさいと感じていた音がいつの間にか気にならなくなっているかもしれませんよ。
「音の豆知識」関連記事は>>こちら
#耳のしあわせラボ